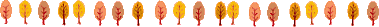
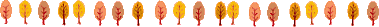
教室は暖かい。
自分のジャンバーを教室の後ろにあるフックにかけ、席につく。寒い場所から暖かい場所に移動すると、ほっぺたや耳が赤くなる。
どちらかというとその変化が顕著に出る私は、自分の頬に両手をあてた。
ホームルームまでは、まだ時間があった。
今朝お隣の安田家のばあちゃんが持たせてくれたホットミルクを思い出し、鞄をあさる。
杏~、今日はしばれるから持ってけ~、と。
言った安田のばあちゃんは、もう76歳だ。小さい頃からばあちゃんだった。
水筒の蓋をコップ代わりに、コポコポ注ぐ。
冷えた体にじんわりとしみこむ温かい牛乳は、朝一番の搾りたてで、新鮮な香りがする。薄皮がどろっと出てきた。
あまり得意ではないが、一緒に飲み込む。喉にすこしひっかかった。
濃厚が売りの、安田牧場の牛乳。
わざわざ市外からも求めてやって来る人がいるのに、私はお隣さんの特権で、一番おいしいのをいただけるのだ。
1杯いくらだったっけと、下世話なことを考えながら、再び蓋に口をつけると、隣の席の馬場さんに話しかけられた。
「うっそ、四宮さん水筒に牛乳!?なんま貴重!しんじらんないわ!」
彼女は今年初めて同じクラスになった子で、よく札幌にも遊びにいったりしているらしく、「今時」な感じだった。
彼女と仲の良い子はうちのクラスに四人ほどいて、明るく気さくで印象は悪くないのだが、物怖じせずになんでも話してくるので、同じクラスになって間もない私は少し苦手意識があった。
「え、そうかな?あったかくておいしいけど…」
「普通やんないっしょ!うける!わや!かわいすぎ~!」
そんなに爆笑されたら恥ずかしい。別に人が何を飲もうか勝手ではないか。
ふと、冷たい空気とともに大きな影が私の席にできた。
「何飲んでんの」
「え?安田のばあちゃんがくれたホットミルク…」
「くれ。寒すぎて死ぬかと思った。」
そういって私の飲みかけのカップと水筒を半ば奪うように手にして二つ後ろの席に行ったのは、やっちょだった。
せっかくおさまりかけていた顔が、また少し、赤くなる。
やっちょとは今年も同じクラスになった。
去年の文化祭の翌日、勇気を出して朝の挨拶をしたら、普通に「おぉ」と返してくれた。
それからは、決して多くはないものの、割と自然に会話している。
席についたやっちょから視線を前に戻すと、ものすごい形相をした馬場さんの顔が、目の前にあった。
「ひっ…!」
「てかさ、なんで山野君とそんな親しげなの!?去年の終わりくらいから急に山野君達と仲良くなったっしょ?なんで!?」
「い、いや、昔からの知り合いっていうか…」
「それならずっと仲いいはずじゃん!!おかしくない!?てかずるくない!?山野君には皆しゃべりかけられないのにさ!」
「私もそんな話さないし…」
「山野君から女子にしゃべりかけることなんてありえないんだから!」
「いや、女子って…」たじたじになる私のもとに正義のヒロインが現れた。
「そこまでよ馬場清美!人の交友関係にチャチャ入れようだなんて、やっぱりどこまでもフテブテしい女ね!!!」
颯爽と腰に手をあてながら現れたのは加奈だった。
加奈と馬場さんは小学校からの喧嘩友達らしいが、今年同じクラスになったことで一層ヒートアップしているようだ。
この二人の言い合いはまだ新学期から半月しか経っていないのにうちのクラスの名物になりつつある。
「出たな井上加奈…!」
「あら、クラスメイトを幽霊のように扱わないでくれる?ただトイレに行って用を足していただけなんだから」
「なんであんたがしゃしゃりでてくんのさ!うちは四宮さんに話しかけてるんだからほっといてよね!」
「お生憎様だけど、もうチャイムがなる時間なのよねー、残念!!お邪魔してごめんなさいね!」
「く…あとで覚えときな…」
「ワンパターンな返しであくびが出てくるわね。もっと日本語を勉強して語彙を増やしたらどう?」
なおも食いつこうとする馬場さんをあっさり交わし、私に笑顔を向けながら自分の席に着く加奈。
渡辺君が「なあなあなあ、語彙ってどういう意味さあ?」と面白そうに聞いていた。
奇跡的に、私は加奈と渡辺君とも同じクラスになった。
それだけではない。
なんと純ちゃんも同じクラスなのだ。
一人だけ隣のクラスになったひろくんは、休み時間ごとにうちのクラスを訪れては、「寂しいよ~」を繰り返している。
どういう風に根回ししたのかは定かではないが、給食もうちのクラスで食べている。
今朝も鞄を持ったまま純ちゃんと教壇で話していたが、チャイムが鳴ったので慌てて隣のクラスへ戻っていった。
中学生最後の学年にして、このメンツが揃ったことはとても喜ばしい。
ただ、純ちゃんの影響もあってかこのクラスだけ受験の年や最高学年といった面影が全くなくなってしまい、完全に他のクラスから浮いてるのだけど。
田舎の中学には色々とイベントが多い。
やれ山登りだそば打ちだじゃがいも祭りだと、学年ごとや学校全体で毎月何かしらの行事がある。
その日は午後の授業を使っての新入生との親睦回だった。
いつものように渡辺君の机を半分占領して給食を食べていたひろくんが、食器を戻してきた純ちゃんに話しかける。
「ねえ純ちゃん、そういえば今日親睦会だよね?準備できた?」
「ああバッチリだぜ。もう三年だからな、今年は少しまじめにやることにした」
毎年新入生の親睦会は、部活ごとにそれぞれ出し物をしたり、二、三年の代表が校風を説明したりする。
純ちゃんは野球部の代表として、何かするらしいのだが…。
「ええっ!?純ちゃんが真面目!?どうしたの!?」
あまり大きくない目をこれでもかと見開くひろくんにごつんと一発あびせると、
「中学最後の年だからな。ここらで一発ドバっと部員集めだ。俺がまじめにやれば男の部員は間違いなく入る。そんでもってヤスでマネージャーを二、三人釣れば完璧だろ」
得意げに言った。
横でうとうとしていたやっちょが迷惑そうに顔をあげた。
「…俺そんな話一言も聞いてないんだけど」
「そりゃそうだろ。言ってねえ!」悪びれることもなくふんぞり返って純ちゃんがこたえる。
「…おい。関係ないだろうが俺は」
「別に何しろってわけじゃねえぞ。去年と同じだって」
「いや~、ヤスはさあ、も、ほおんと、宝の持ち腐れなんだわ。黙って歩いてるだけで騒がれるんだからさあ。オイラも騒がれたいねえ」
渡辺君がおどけるのを睨んで
「じゃあ変われよ」と言うやっちょを無視し、
「ぜひよく働きそうな奴を釣ってくれ!できれば飯作るのがうまい奴がいいな!合宿で役立つから!」
と。純ちゃんは満足そうにやっちょの肩をたたいた。
ひろくんはひろくんで、「僕はね、笑うとえくぼが出来る子がいいな~」と嬉しそうに話し、
「浩明は関係ねえだろ」とまた純ちゃんに小突かれていた。
当の本人はふて寝を決め込んだようで、ピクリとも動かない。
そういえば、去年も五月を過ぎた辺りだったろうか。
やっちょのクラス(私のクラスでもあったけど)の入り口にはそわそわした女の子達がどの休み時間でも十人くらいは訪れていた。
そこに純ちゃんが入り浸っていたため、やっちょと“お近づき”になろうとした新入生が、将を射んとすればまず馬のごとく、野球部のマネージャーをこぞって志願していた。
後日、強豪野球部の練習についていけず続々とやめていったらしいが。
ましてや今年なんてまだ入学して二週間ほどしか経っていない新入生が、どこからかやっちょの噂を聞きつけてちらほらと教室の窓からやっちょを探しているのだ。
純ちゃんが去年と同じ展開を期待するのは単純だけど、頷ける話でもある。
純ちゃんの陰謀により、私達の席は見事に集合しているため会話は筒抜けだ。
私と加奈も会話に参加したりしなかったりするのだが、今日はあまり参加できそうな会話でもなかったので、二人で宇宙人の存在の可否について話していた。
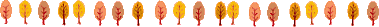
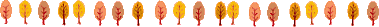
↓クリックいただけるとありがたいです↓