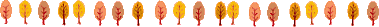
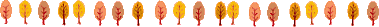
新入生との親睦回はなかなかの盛り上がりを見せた。
純ちゃんはなんと舞台上でバッター用ストラックアウトをして、見事全パネルを打ち抜いた。
それだけでもすごかったのに、その後トスバッティングでくす球を割るというパフォーマンスまで見せ、
強豪野球部の四番を一年から守り続けている実力を私達に見せ付けてくれた。
渡辺君の指笛も最高潮に響いていた。
先生達は閉口していたし、その後純ちゃんはしばらく帰ってこなかったから、多分許可が下りていなかったようだけど。
新入生はもちろん、在校生も大盛り上がりで、野球部への入部希望者が増えるだろうことは、必至だった。
野球部での純ちゃんをまだ見たことがなかったが、真剣な顔はすごく男前で、多分また純ちゃんの人気は上がるだろうと予想がつく。
そんな彼の「友人」でいられることを誇らしく感じた。
親睦回も終わり、部活動をしていない生徒は帰り支度を始める。
所属するバドミントン部の部室に向かおうとする私に、やっちょが話しかけてきた。
「水筒、安田のばあちゃんに返しとくから」
すっかり忘れていた。
「うんありがとう。おいしかったって伝えといて」
「四宮は飲まなかったって言っとく」
「ちゃんと私も飲んだってば。おいしかったってば」
「自分で言えば」
口の端を上げながら、教室を出て行った。
後ろ姿は、純ちゃんほど大きくはないものの、割とガッシリとしていて均整がとれている。
猫背を直せばもっとすっきり見えるのに、もったいない。
やっちょは部活がスキー部なので、冬以外はほぼ筋トレしかやることがない。
どうやらその筋トレが面倒らしく、春から秋にかけては帰宅部員と同じ生活リズムだ。
寒がりなのに何故かスキー部で、しかも実力はかなり高く、何度か地区優勝している。
昔から感じていたのだが、やっちょは、変だ。
つかみどころがないし、無愛想でほとんどしゃべらない。
服とかに気を使うわけでもないし、髪だっていつもボサボサで。
かなり整っていると噂の顔も、半分くらいが隠れてしまっている。
だけど。だからこそ。
その人の目を気にしない超然とした態度が、逆に人をひきつける圧倒的な存在感になっているという事実に。
気づいたのは、つい最近だ。
付け加えて言えば、実は私もひきつけられている中の一人。
あの文化祭の日に生まれた感情。
知らず知らずのうちに彼を目で追っている自分。
実際、意識してやっちょを見てみると、もう、駄目だった。
そういう目で見てしまうと、驚くくらい、格好良く見えてしまって、駄目だった。
何もする気はなかった。
やっと戻れたこの関係を、また自分から手放すようなことは絶対にしたくない。
そう思う理性とは裏腹に、膨らんでいく感情を。最近、持て余している。
はっきり言って、自分には無縁と思っていたこの現象。
顔を見たり、声を聞いたり、森の匂いを感じると、それだけで嬉しくて、泣きたくて。本当に、駄目になってしまう。
そんな自分が気持ち悪くてしょうがない。
「杏~。生きてる?」
加奈が肩越しに私を見上げながらニヤニヤしている。
「だ、大丈夫だよ。何?その笑い方。気持ち悪いなあ」
「ほうほう、そういうことを言うのねその口は」
一層ニヤニヤしながら加奈は教室をさっと見渡して、
「じゃあ教えてあげない」と言い放つ。
「な、何のこと?」恐る恐る聞くと、
「昼間の続きよ。どうやって桜井君が馬場清美を取り込んだか。気になるでしょ?」
表情を変えないで彼女は言った。
気になる。
すごく気になる。
でも、そこで思い切り食いついて。
「あんたまさか…」みたいなパターンに陥るのは嫌だ。
純ちゃんやひろくんと仲良くなった加奈に私の気持ちがばれてしまったら、きっとどこかのバランスが崩れてしまう気がして、必死に秘密にしてきた。
本当は、加奈に全てを話したいのに。必死に、必死に、隠してきた。
だから、他に興味があるという表情で、
「確かにあれだけコロッと態度が変わるのは気になるよね。ひろくん何て言ったの?」と聞く。
右目を薄くしてしばらく私を観察していた加奈だったが、短くため息をつくと言葉を吐き出した。
「山野君の家に遊びに行くらしいわよ。部活が終わってから馬場清美も引き連れて」
ちょっと。ほんのちょっと、目眩を覚えた。
純ちゃんが馬場さんを気に入って連れまわすというのも相当こたえるが、
やっちょの家に馬場さんが上がるということが嫌な自分がいたことの方に、ショックを受けた。
やっちょは私の所有物なんかじゃないのに。
やっちょは、そうそう他人を家に上げない。純ちゃん達はたまに行くらしいが、私は小学生の時、2、3回程しか行ったことがない。
5年間も毎日一緒にいたのに、だ。
それが、こうもあっさり家に上げるというのは、実は前から2人は仲が良かったのだろうか。
私が知らなかっただけで。
「うっそ~」
思考を突然さえぎられて顔を上げると、加奈が少し不機嫌な顔をしながら続けた。
「本当は、山野君の幼少期の写真集を餌につったらしいわよ。あの女、山野君のファンクラブとか作ってるみたいだし」
「ファンクラブって…」
少しほっとしたが、それはそれで驚く。ファンクラブまであったのか。
「ミーハーもいいとこよね。本当、虫唾が走るわ」本当に震えている加奈に少し笑ってしまう。
「そこまで言わなくても」
「ま、あんたも気をつけなさいよ?」
「…何で?」
「今朝みたいに馬場清美に絡まれることが増えるでしょうから」肩をすくめて加奈が言う。
「だから、何で?」
「今朝の水筒の蓋。あれがだめよ」
なんせ教室で間接キスを見せ付けられたんだから。
びっくりした。
トイレに行っていた加奈がなぜそんなことを知っているのかよりも。別に、同じカップで何かを飲むとか、日常茶飯事ではないのか。
「いや、か、間接…とか、そういうんじゃないでしょ、あれは!」
「桜井君とか渡辺君ならいいのよ。山野君だからだめなのよ。山野君から動いたから。
皆薄々感じてはいたでしょうがね、今朝のあれで、実証されてしまったのよ。
あんたが山野君から話しかけられる、あまつさえ、間接キスも厭わない、唯一の女子だってことがね!!!!」
腰に手をあて、私を指差すその姿は、さながら謎解きのラストに犯人を言い当てる、名探偵のようで。
「女子って…そんなもんかなあ」
私はいまいち納得が出来なかった。
確かにやっちょは普段どの女子ともほとんど会話をしないが、必要最低限のことはきちんと話す。
しかも、彼は私のことを「女子」という括りではなく、「四宮杏」としてみてくれているわけだから、女子という概念はないはずなのだ。
まあそんな話は馬場さんたちが知るわけもないのは確かだが。
「そんなもんなのよ、女って。杏はそこら辺相当疎いからだめよね」
ため息をつかれても私にはどうしようもない話だ。
色々と突っ込んで話を聞いてみたかったが、この友人は肝心なところでいつもはぐらかす性質を持っている。
あまり深く付き合わずに、部活へと走った。
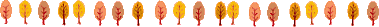
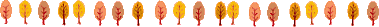
↓クリックいただけるとありがたいです↓